close
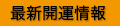
|
| 商品詳細説明 | 素材やいわれの説明 |
戻る |
 |
 |
 |
 |
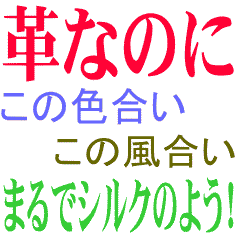 |


| *革とは思えないほど、軽くてやわらかく、手触りが絹のようです。さすがに京都の伝統工芸、 京友禅染めで雅やかな色彩ですね。革もこんな感じに染められるんですね! *ふわふわした手触りで使い勝手がよく楽しくお買い物ができました。 *触った感じが、さらさらしていて柔らかい。持っていて気持ちがいい。あと和風の柄なのかなと 思っていましたが、実物を手にしたらアジアンテイストな感じで私の好みでした。 年齢をあまり選ばないのではないかなと思います。 *使って3ヶ月いい色になってきました。革って人の手が加わるとこんなに、かわるんですね。 日本の革ってすばらしい。と思うのはやはり日本人かな。 |

| 江戸時代中期の初め、扇絵師の宮崎友禅斎(みやざきゆうぜんさい) によって始められたとされています。この染めの最大の特徴は、全体を優美にくくる 極端に白い細い線です。 友禅糊で、まづ白に抜きたい絵柄を書き、その上に一色一色、色を乗せていき 地色を吹き付けます。そして最後に水洗いすることによって友禅のりで一番 はじめにかかれた部分のみが、水で洗い流されます。流された部分が白く浮きでて 通常のプリントでは、表現仕切れない微妙な白い線が出てきます。 この技法が友禅染めです。 古くから京都ではこの技法を用い高価な着物を作っていましたが、この技法を 革に応用し革本来の風合いを生かし友禅染めのすばらしい色彩感を最大限に 表現したのが、この京都本革製友禅染めです。 又、染料には草木染料をモチーフに配色されていますので、自然の感触が 目でも堪能できます。 |
染色工程
染料合わせ

|

|
 |
| このとき微妙な濃淡の色加減を、わずかなデータと肉眼とかんで 色加減を決めていきます。まさに職人技です。天候と湿度に よって大きく左右されるばかりでなく、仕上がるまでその色加減が わからないため、正に真剣勝負です。 |
出来上がりの友禅染め用染料は一日たてば使えなくなるため
全体の分量も染める料にによって、たいへん気を配ります。
染色(手な染)
 |
まず、糸のくくりを出す友禅のりを、型の 上から置きますへらを使い革に塗り込みます。 最後、水洗いするとその部分だけが 白く浮き出ます(下左参照) |
 |
その次に染料を一色一色革に染色していきます 型を革の上に置き、適度の染料が付いた へらを、一気に上から下へおろします このタイミングと、染料の料のバランスが腕の 見せ所、スピードが遅すぎると線が太くなり、 早すぎると線がやせます。この技が機械では 表現しきれない商品の味となり、手捺染独特の 風合いがかもしだされます。 作業中はまさに真剣勝負、黙々と作業が 続きます。 |
 |
1色1色を重ね、徐々に模様が できあがってきます。 一番はじめに置いた細い線がたくさんある型 この部分が水洗いされると白く 浮かび上がります。 いわゆるこれが友禅染めです だいたい4枚から5枚、型を重ねて、 柄を完成させます。 |
この部分が白くなります |
→ |  |
→ |  |
 |
 |
| この後友禅の最大の特徴の白い細い線をだすため、水洗いをします 水洗いしたことによって、糊の部分が流され白の色が浮かび上がります 弊社で取り扱う、友禅染めはこの後、乾燥機で乾かすことは絶対に しません。なぜなら急に乾燥させた革は収縮率が大きくかわり、風合いや 色合いを保証できません あくまでも自然乾燥にこだわっています。天候と仕上がり時期を 見極め約1週間から2週間で完成します。 |
| 戻る |
|
||||
|